
横浜でクラウディア・カルディナーレのことを話してきました。「懐かしの俳優たち」と銘打っての2回目です。きっかけは今年の初めにジーナ・ロッロブジジダの訃報に触れたこと。新聞にも追悼記事が出たのですが、日本のものは何かが足りない。調べてみれば、彼女の経歴の大切な部分がすっかり抜け落ちていて、ただ綺麗なだけの女優さんだったという思い出ばなしばかり。そういうわけで、デビューのころからの作品をふりかえり、最近の消息もおいかけてみたら、なんだかその人生と仕事が絡み合いながら浮かび上がってきたのです。
なんだか目が覚めたような気がしました。そういう視点を今まで持ったことがなかったのです。いや、映画を見始めたころにはそれだけだった。かっこいい男優、うつくしい女優、それも洋画を好んで、ただただ見惚れるだけだった。邦画はバカにしていたのですが、77年の『離れ瞽女おりん』で目が覚めました。日本の映画も捨てたもんじゃない。ちょうどアメリカでは『スターウォーズ』や『未知との遭遇』が公開されたころです(日本公開は78年)。ニューシネマからスペクタクル映画への回帰が始まっていた頃です。
おっと話がそれました。カルディナーレのことです。ぼくが彼女を発見するのはフェリーニとヴィスコンティの作品です。それも同じ1963年の『8½』のクラウディアと『山猫』のアンジェリカは忘らない映画体験でした。
フェリーニのクラウディアは、最初は幽霊のように登場します。まずは湯治場での飲泉のシーン。その白衣すがたはこの世のものとは思われない美しさでした。そして主人公のグイードの想像のなか。泉の女として白衣を着たままで呼び出され、映画監督の妄想のなかで妄想された自分の役どころに笑い出してしまう。そして「秩序を与えたいの/お片づけをしたいの。汚れを取り払いたいの/お掃除したいの」(Voglio fare ordine. Voglio fare pulizia.)と繰り返します。そして最後は、テストフィルムのチェックシーンで試写室に、今度は血も肉もある存在として登場する、クラウディアという同名の女優となります。
この最後の登場シーンで、クラウディアとグイード(マルチェッロ・マストロヤンニ)の会話が興味深い。じつはカルディナーレ40歳のときの娘クラウディア・スクイティエーリ(今は美術史家)もまた、母のことを語るときにこのシーンを引用して、フェリーニは母クラウディアが将来答えることになる問いを投げかけているというのです。見てみましょう。

グイード:なんて綺麗なんだ。ひるんでしまう。まるで学生のように心臓がドキドキしてしまう。信じてくれないのかい。きみから伝わってくる尊敬の念は、すごく真剣で、ほんとうに深いよね、クラウディア。一体誰に恋しているんだ?誰と付き合っているんだい?誰のことを大切に思ってるんだ?
クラウディア:あなたよ。
グイード:ほんとうにいい時に来てくれた。でもさ、その微笑みはどういう意味なの。裁こうとしているのか、許しなのか、からかいなのか、判らない。Guido: Quanto sei bella, mi metti soggezione, mi fai battere il cuore come un collegiale. Non ci credi, eh? Che rispetto vero, profondo, comunichi. Claudia... Di chi sei innamorata? Con chi stai? A chi vuoi bene?
Claudia: A te.
Guido: Sei arrivata proprio in tempo, sai. Ma perché sorridi così? Non si capisce mai se giudichi, se assolvi, se mi stai prendendo in giro. [...]
ここには、監督と女優の理想的であり、それゆえに受け入れがたい関係が見られます。フェリーニは、クラウディア・カルディナーレという女優を、同じクラウディアという名前の女優として登場させると、その美しさを称揚します(なんて綺麗なんだ)。その美しさには「怯んでしまう」(Mi metti in soggezione)というのです。しかし、そこにはただ美しさだけがあるのではない。彼女からは監督への「敬意」(rispetto)が感じられるというのです。それも「本物」(vero)で「深い」(profondo)な敬意。
この「敬意」は、まるで恋に落ちた者のものようです。だから「誰に恋しているの?」(Di chi sei innamorata)「誰のことが大切なの?」(A chi vuoi bene?)と続くのです。クラウディは女優ですから模範的な回答をします。「あなたよ」(A te.)。
しかしグイードはその模範的な回答と微笑みが耐えられません。監督としてのインスピレーションが枯渇し、創造の危機にあると感じているからです。だから言います。「その微笑みはどういう意味なの?裁こうとしているのか、許しなのか、からかいなのか、判らない」(Ma perché sorridi così? Non si capisce mai se giudichi, se assolvi, se mi stai prendendo in giro. )。
暗示されているのは、グイードが自分の仕事に自信を失いかけていることであり、愛する人生の伴侶がありながら浮気をしてしまっている後ろめたさ。仕事と伴侶があるのだから、それで満足すればよいはずなのに、それができない。その気持ちが続くグイードのクラウディアへの問いかけに表れます。
グイード:(クラウディア)きみならさ、全てを捨てて人生をやりなおすことができるかい。たったひとつのことを選んで、ひとつだけに誠実でいて、それを生きる理由にするんだ。そんなことができるかい。そのひとつがすべてになる。きみの誠実さがそのひとつのものを永遠にする。そんなことができるかい。
Guido: Tu saresti capace di piantare tutto e ricominciare la vita da capo? Di scegliere una cosa, una cosa sola e di essere fedele a quella, riuscire a farla diventare la ragione della tua vita, una cosa che raccolga tutto, che diventi tutto proprio perché è la tua fedeltà che la fa diventare infinita, saresti capace?.
「たったひとつだけを選ぶこと」(scegliere una cosa sola)ができるかという、グイードの問いかけにクラウディアは答えることがありません。しかし、カルディナーレの娘クラウディア・スクイティエーリによれば、母のクラウディアは、父となるパスクワーレ・スクイティエーリと出会ったとき、「たったひとつのこと」を選び取ることになるというのです。どういうことか?
カルディナーレは、戦後イタリア映画の立役者でプロデューサーのフランコ・クリスタルディの庇護のもと、ヴィデス社のスターシステムのなかで成功をおさめてきました。しかしそれは、みずから選んだというよりは母の意向が大きかった。チュニス近郊のラ・グレット生まれの彼女は、チュニジアのイタリアコミュニティで開かれた美人コンテストで「チュニジアで最も美しいイタリア女性」に選出され、ヴェネツィア映画祭に招待され、そこでクリスタルディに見出されるのです。
本人は女優よりも「探検家」になりたかったと言うのですが、結果的には女優として世界を「探検」することになります。それはそれでよかった。しかし、恋はどうなのか。じつは、クラウディア・カルディナーレは大スターになっても、恋を知らずに来ている。恋に関しては、惚れたとか振られたとかいうもの生やさしいものではなく、トラウマ的な経験をしている。デビューする直前に乱暴されて妊娠。家族と出産を決意するも、もうデビューができないと諦めかけたとき、クリスタルディが救いの手を差し伸べる。密かにロンドンに送り、そこで出産させると、生まれた子供は彼女の弟だということにしたのです。
恋どころではない。フェリーニのクラウディアの依代となったクラウディア本人は、じつのところ「たったひとり」を選んで一生愛するような恋をまだ知りません。だからグイード/マストロヤンニの問いかけに答えることができない。答えることになるのは、1974年の『I guappi 』*1 におけるパスクワーレ・スクイティエーリとの出会い。そしてその出会いから、1978年、娘のクラウディアが生まれます。しかし彼女の母と父は結婚することがない。だから娘はその母の名前クラウディアをもらい(祖父の名前はよくあるが、母の名前というのは聞いたことがない!)、父の姓スクイティエーリを名乗ることになるのです。
いやはや、この話には驚きました。フェリーニは自分の映画のなかに自分自身の分身(グイード/マストロヤンニ)を登場させていただけではなく、当時のトップスターであるクラウディア・カルディナーレの未来の人生までをも取り込んでいたというわけです。
そんな母クラウディアのことをみごとに言い当てた映画監督として、娘クラウディアが挙げているのがヴィスコンティです。フェリーニの作品には一度だけの出演でしたが、ヴィスコンティには何本か出演しています。フランコ・クリスタルディが彼の多くの作品をプロデュースしているというのもあるのでしょう。最初に登場するのは『若者のすべて』(1960)です。クラウディアにはすでに主演映画がありましたが、名のある監督のもとで、アラン・ドロンやアニー・ジラルドらの国際的なキャストと共演するのは、戦略的なものだったでしょう。
しかし、クラウディアはここでヴィスコンティの目にとまります。『山猫』(1963)のアンジェリカに抜擢されるのです。同じ1963年には『8½』、コメンチーニの『ブーベの恋人』が公開されています。特筆すべきは、この年のフェリーニ、ヴィスコンティ、コメンチーニの作品において、それまでずっと穏当な女性の声に吹き替えられてきたカルディナーレが、はじめて地声で演技をしていること。その理由は、声質が低く掠れていること。もうひとつはイタリア語がネイティブではないこと。
カルディナーレの母語はフランス語、アラビア語、そしてシチリア語。イタリア語は大きくなってから学んだものなので、最初はそんなに自然ではなかったのでしょう。個性的な声質も、最初はよく思われなかったのでしょう。さいわいイタリア映画界では、吹き替えがあたりまえだったこともあり、その出世作の『鞄を持った女』などはアドリアーナ・アスティがみごとなミラノなまりで吹き替えしてくれています。
しかし、そんなカルディナーレの地声を最初に採用したのはフェリーニであり、その個性を認めたのがヴィスコンティであり、そこにコメンチーニが続くことになります。実際、『山猫』のアンジェリカの役柄は、新興ブルジョワの娘で母親はいかがわしい商売をしていたものの、ハッとするほどの美しさがあるというもの。だとすれば、カルディナーレの見た目とその声がみごとにはまるではありませんか。たとえば、あの食事のシーンでタンクレーディ/アラン・ドロンのジョークに下品な大笑いをしてしまうところ。あの声であの笑いが響き渡るところこそは、新興ブルジョワのおぞましさが気取った貴族社会を凌駕してゆくことを、みごとなまでに象徴していたではありませんか。

そんなカルディナーレのことを、ヴィスコンティはこんなふうに語っているといいます。娘の編集したアンソロジーから引用しておきましょう。
今日、クラウディア・カルディナーレは素晴らしい猫のようだ。ペルシャ猫とかトラ猫。いたずらにサロンのクッションを引っ掻く猫のように見える。けれども、わたしがはっきりと感じているのは、近いうちに人々はクラウディアが虎であることに気づくだろうということ。その鋭い爪を立てて、飼い主を殺しかねない、そんな虎だということを。
虎となったカルディナーレの爪でザクっと殺される「飼い主」と言えば、フランコ・クリスタルディですね。カルディナーレはまさにクリスタルディのヴィデス社が総力をあげて育て上げたスターなのですが、隠し子がいて未婚の母であることが記事になるころ、このプロデューサーは妻と別れ、1966年にアメリカでカルディナーレと結婚しています(イタリアではまだ無理だったんですね。離婚法ができるのはもう少し後のこと)。しかし、カルディナーレのほうには愛がない。尊敬はしていたものの、結婚は押し付けられた戦略のようなものに感じたのでしょう。
だから、1974年パスクワーレ・スクィエティエーリと出会い、自分が籠の鳥だったことを理解したとき、自分の人生からトリノのプロデューサーとそのヴィデス社を追い出してしまう。ちょうどアルベルト・ソルデイと共演したルイージ・ザンパの『Bello, onesto, emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata(美男子で、正直者の、オーストリア移民なら純潔な同郷の女と結婚するのだろう)』(1971)のなかで、暴力的なポン引きから逃げ出して空港で飛行機に飛び乗って、将来をともに生きる男のもとへと飛び立つカルメーラさながらに*2、ニューヨークの空港に降り立つと、当時はアメリカにいたスクイエティエーリに電話をしたというのです。
もちろん高い代償を払うことになるのですが、彼女にとっては高が知れている。しばらく映画界から干されることになるのですが、映画の方が彼女を放っておくはずがない。その後、パスクワーレ・スクイエティエーリとは11本、ほかにもフランコ・ゼリレッリ、マルコ・ベロッキオ、リリアーナ・カヴァーニ、マヌエル・デ・オリヴェエーラ、ブレーク・エドワード、ヴェルナー・ヘルツォーグなどの名匠たちの作品に呼ばれることになるわけです。
それにしてもつくづく思うのは、映画というのが結局のところ人なんだということ。ヴィスコンティはそれを「チネマ・アントロポモリフィコ」と呼びましたが、それは人間が神を創造するときに、人の似姿をした存在(ディオ・アントロポモフィコ)として構想したところに端を発する表現。おそらくあらゆる芸術作品は人の姿をしているのでしょう。風景画だって、人の視線を枠組みなかに表現したもの。これが映画になるとショット、イタリア語ではインクワドラトゥーラ(inquadratura:枠決め、ショットの構図)となります。そのショットのなかに、人が立ち、動き、話し、まなざしを交わす。カメラの前の人も、カメラの背後の人も、そこにそれぞれの人生を少しずつ投影する。そのいつもの影が交わるところに立ち上がるのが、チネマ・アントロポモルフィコというものなのかもしれません。
クラウディア・カルディナーレのような人は、まさにそんなチネマに、思いがけない輝きを放つ命の吹き込できたわけです。いや、まだまだこれからも吹き込んでくれるに違いありません。
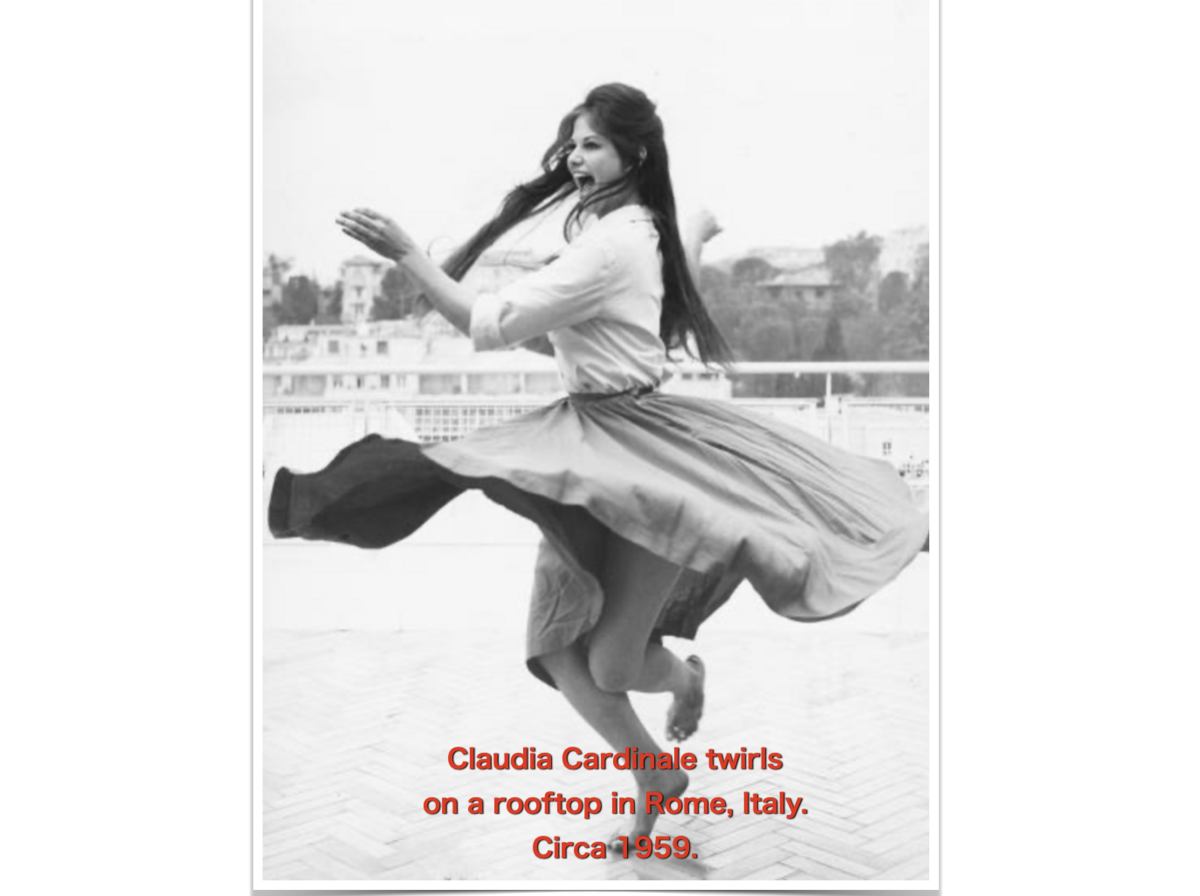

![鞄を持った女 HDリマスター [Blu-ray] 鞄を持った女 HDリマスター [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/616DgHeojFL._SL500_.jpg)
![8 1/2 [Blu-ray] 8 1/2 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51Nqdrn3VlL._SL500_.jpg)

![熊座の淡き星影 [DVD] 熊座の淡き星影 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51V4ZN7Y8JL._SL500_.jpg)
![Bello Onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata [Italian Edition] [DVD] Bello Onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata [Italian Edition] [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/5163pfTMDjL._SL500_.jpg)
![I Guappi [DVD] [Import] I Guappi [DVD] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/41sT1XnF0pL._SL500_.jpg)